|
川と川の大喧嘩
 船上山の峰続きに、勝田が山、兜が山、矢筈が山がある。むかし、その山々から流れている勝田川と矢筈川が、川の水が多い少ないで、大喧嘩をした。矢筈川が腹をたてて、さかんに矢を射たが、どうしても勝つことが出来ず負けてしまった。 船上山の峰続きに、勝田が山、兜が山、矢筈が山がある。むかし、その山々から流れている勝田川と矢筈川が、川の水が多い少ないで、大喧嘩をした。矢筈川が腹をたてて、さかんに矢を射たが、どうしても勝つことが出来ず負けてしまった。
そこで勝った方の川の山を勝田が山、矢をたくさん持っていて勝つはずだった川の山を矢筈が山といい、この勝負をじっと見ていた真ん中の山が「勝田が山には兜を脱ぐわい」といったので、兜が山と名がついたそうな。今では、矢筈川は大門橋の所までで勝田川と合流し、勝田川が海まで続いています。
古屋のむる
昔しなぁ。貧乏なお爺さんと、お婆さんが、一生懸命に子牛を飼っておってなぁ、大分大きくなったので、売ったらお金がどっさり入ると思って、楽しみにしていたそおな。
あるくらい晩に、山奥に住んでいる虎狼が出てきて、牛小屋のわらの中に隠れ、お爺さん夫婦が寝込んだら、取って食ったらあか、と思っていた。
ちょうどその晩、悪い博労が、やはり、お爺さん達が寝たら、こっそり牛を盗んで、ひともうけしようと、家の外で待っていた。
そしたら雨が降り出し、お婆さんが「こんな晩にゃ、虎狼が出りゃせんだらぁかいな」と話しかけた。
そしたら、お爺さんは「虎狼より、むる(雨もり)の方が恐てぇわい」といった。
 これを牛小屋から聞いていた虎狼が「この家には、何っちゅう恐といもんがおるだらぁかい、こうしちゃおられんぞ」と思って、一目散に牛小屋から外へ逃げ出した。 これを牛小屋から聞いていた虎狼が「この家には、何っちゅう恐といもんがおるだらぁかい、こうしちゃおられんぞ」と思って、一目散に牛小屋から外へ逃げ出した。
そしたら、外にいた博労が、牛が飛び出したと思って、その虎狼の背に飛び乗って、放しては大変だと、首のしがみついて放さんだけ、虎狼はむるという恐とい奴が、さばったと思って、だら、だら、だらっと駆けるけど、恐とい奴は放れりゃせず、山の方へ向かって逃げるうち、松の木の根っこに穴があり、その松にこすり付けたら、そいつは、ようやく離れて、穴の中へ落ち込んだ。
やれやれ、これで助かったわい、と思って走っていたら、こんどは猿に出会った。虎狼が「なんと今夜は恐といもんに捕って、もう少しでしごされるとこだった」というと、猿が、「どんなもんだったえ」と聞いてくだけ,
「むるといってなぁ、さばったら最後、なかなか放れんもんだったが、一本松の所で、こすり落として、穴の中に落ちたので、やっと助かったわい」というと、猿が
「そんな恐といもんは、見たことがないが、連れて行って見せてくれ」というので、その穴まで引き返してみると、穴の中は真暗で、博労がくたびれて寝ていた。博労は、大いびきをかいており「それ見い、むるが落ちてうずろうとるがな」と虎狼が言うので、いくら猿が穴の中をのぞいて見ても暗くて何も見えず、手さぐりしてもとどかず尻尾が長いので、それを穴の中に入れて振り回したところ博労の顔に尻尾が当ったもんだから博労は目をさまし、それを牛の尻尾だと思って、一生懸命に引っ張ったところ、上から猿が「むるに捕まった、助けてくれー」っていうだけ、虎狼も手をかして引っ張り合った。そしたら猿の尻尾がちぎれて、真っ赤な血が出た。猿の尻はそれから赤くなり、引っ張るのにあまり力んだので猿の顔も真っ赤になった。
それから、猿は長い尻尾だったのが、この時切れてしまったので、短くなってしまった、と。
弁慶のこぶ取り岩
昔、船上山の岩山にはこぶが四つあり、どう見ても、みっともないものだった。
船上山の山伏が、弁慶に向かって「お前は力持ちだが、このこぶを取ることができるか」といった。
弁慶はいばって「こんなこぶ岩、なんでもないわ、引きちぎって一里や二里は投げて見せる」といい、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、したそうな。
その岩が、大熊の西の釈迦平(しゃかなる)に二つ、山川の池山家の下手に一つ、立子越しに一つ飛んできて、この岩は今でも残っている。
その大きさは人間が十人ぐらいは乗ることが出来るという。
足王さん
足王さんは、慶應の昔大父木地の清兵衛さんが、奥さんの足が悪く、足を治してやろうと作州の須賀平という所までお参りするため何日も歩いて勧請して来たのが始まりだといわれる。
その後、小さなほこらを建てて祭りおかげを受けて足が治った人が後をたたず、霊験あらたかといわれ、遠近問わず参拝者が続いた。
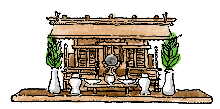 新しい話では、大父木地に耕作という若者が、リュウマチをわずらい、長い間ぶらぶら遊んでいたが、この足王さんに願掛けをして「治ったら新しいやしろを建てます」と一生懸命にお祈りをした。 新しい話では、大父木地に耕作という若者が、リュウマチをわずらい、長い間ぶらぶら遊んでいたが、この足王さんに願掛けをして「治ったら新しいやしろを建てます」と一生懸命にお祈りをした。
耕作は戦争中の徴兵検査に甲種合格となり入営することになった。ところが、まだ新しいおやしろを建てておらず、足王さんにお参りして「まことに申し訳ないが、徴兵から帰ったら、必ずやしろを建てます」といって戦地に赴いた。
戦いは利あらず沖縄で戦死した。父母の悲しみはひと通りではなく、せめて息子の願いをかなえてやろうと、足王さんを改築し息子の供養とした。
七化け八化け
昔のことだったが、以西の博労が節季(せき)おそくなってもどる途中、村はづれの井手川にさしかかると狐がおり、あんどろ(川藻)をかぶって、いい女房に化けようとしていた。それを見つけた博労が「おい、わりゃ、どのくらい化けかたを知っとるか」と聞くと、狐は「七化け知っとる」と答えた。
 すると博労は「ほう、そんなら、まだ一化け足らんなぁ、そっで尾が出とるわい」 すると博労は「ほう、そんなら、まだ一化け足らんなぁ、そっで尾が出とるわい」
驚いた様子で狐が
「お前、なんぼ知ってござる」と聞くと、博労は「俺は八化け知っとるぞ」という。
そこで狐は、博労に化けを習わせてもらうことになった。
「その代わり大歳の夜に、分限者(ぶげんしゃ…お金持ちのこと)の家からもちを盗んでこい」と博労が命令した。
そこで狐は、猫窓から家の中にしのびこみ一つ、二つ、三つと、供えをとって博労にわたした。
博労が「まだえっとあるか」と聞くと狐は「んにゃ、まんだ一つ供えがある」と答えた。狐が最後の供えを取りに入ると博労は、猫窓の穴をふさいで狐をでられないようにしてしまった。
家の中の狐は「八化殿、八化殿」必死に呼んで出口を探そうとするが、なかなか見つからず、博労も返事をせず、その叫び声も、段々大きくなり、とうとう分限者の旦那が目を覚ましてしまった。
男衆が、そこへかけつけたところ、小僧っこが、餅を抱えて部屋中を駆けまわっていたので「なんでお前 餅を抱えて駆けまわっとるか」と、棒切れで叩き殺してしまった。すると、何と、その小僧っ子は狐であったということだ。
船上山の化物退治
なんと、昔、あったそうな。
山の下の方から侍が大熊村まで上がって来て、「今日は船上山に上がろうと思うが、どれほどの道程があるか」って、村の人に聞いた。
そこの年寄りが、「こりゃ、お侍さん、これから船上山にあがんなはんな、船上山には、晩に上がって戻ったものがないけえ。今晩は家に泊まって、明日お参りしなはれ」と止めた。
だが、侍は言うことを聞かず、山の奥へ上がって、今度は船上山の下に家が五、六軒ある山川木地という所で、また、「ここから船上山に上がろうと思うが」と尋ねたら、「やめなはれ、これから上がれば暗くなってしまって、化物が出て、あんたの命をとってしまうけえ」とだいぶ止めたふうだけど、侍は聞かずに山に上がって行った。
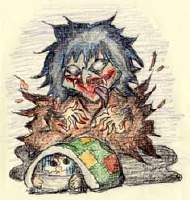 茶園原まで上がったら、船上山で茶を沸かす爺が下りて来て、「はあ、旦那さん、もはや、これから山にゃ上がれんけ、いっしょに下りょいな」と、言ったが、侍は、「そんな化物が出りゃ退治してやる」と、しゃにむに上がって、猿坂に向かった。 茶園原まで上がったら、船上山で茶を沸かす爺が下りて来て、「はあ、旦那さん、もはや、これから山にゃ上がれんけ、いっしょに下りょいな」と、言ったが、侍は、「そんな化物が出りゃ退治してやる」と、しゃにむに上がって、猿坂に向かった。
侍は「急な、えらい所だわい」と思った。そしたら猿が二匹、大きな石に乗っとって、侍を拝むだけ、侍は「こいつが、化物だわい」と、思って思案して、立っておったけど、この猿はなんにも手出しをせず、ただ、頼むように拝むだけ、「ええ、まあ、この石を起こしてみたれ」と思って、侍だから力はあるし、起こして見た。ところが、石の下に、小猿が三匹出て来た。大変喜んだ猿は親子連れで、山の方へガサガサ上がって行った。
侍はそれから、また上がって行き、上の原に着いた。一の木戸といって、大きな石の段々があってえらい急な坂道で、石の間みたいなところを伝って、伸び上がって見たら、茶沸かし爺のおった小屋が見える。火がちらちら燃えておるので、そこで一休みし、くたびれて居眠りしていたところ、山の方から、またガサガサいうだけ「こりゃ今度こそ化物が出ただらあか」と、独り言を言っておったら、また、猿が親子連れで出て来て、茅づとの大きなやつを持って来て、侍を拝んで去ってしまった。
上がりかけに、猿を助けてやったので、恩返しに来たんだなあ」と、茅づとを開けても見ず、腰もとに置いて焚火にあたっていたら、また外から「ケラケラ」笑う声がするので、こいつが化物だわいと思って「なんだ、性あるか、無いか」と声かけたところ「お前の首が欲しくて、来たわい」という。「ほう、取れるもんなら取ってみい」といったら、入って来たのは、耳まで口の裂けた女だ。じわりじわりと、そばにやって来る。これ以上、近寄って来たら、刀で斬り倒そうと身構えた。いざ、斬りかかったが、どうしても、うまくいかない。刀を振り回しているうち、いい按配に女の額に刀が当たったと思ったら、なんと「ピィーン」と音がして、刀が手から離れて飛んだ。
これはしくじったぁ、これで命を取られた、と思いながら、ふと猿のくれた茅づとを手に取り振り回したら、その女の額口に当たった。そしたら、血がパアーッと散って、急に女の姿が消えてしまった。
不思議に思って、猿からもらったつとを出して見たら、なんとナメクジがいっぱい。「ほんに、ナメクジは、マムシの毒と聞いていたが、あの化物はマムシだったかも知れんわい」と考えるうちに夜が明け下の村の者が、上がって来て「旦那さん、どんな化物が出たかな」って聞いた。
「おお、化物が出て、もうちょっとで命を取られる所だっただがあー」と何もかにもを話し、「これから跡をつけて行って、化物を退治したろうと思っ取るわい」と、村人と山を伝って上がりよったら、奥の岩の間に洞穴があり、化物の体があまりに大きいので、頭だけつっ込んで寝ている。そこで侍と村人は力を合わして、退治した。
これはマムシの古い古い奴のツチノコっちゅうもんで、そいつを切ったら材木みたいに、ごろんごろんと谷底に落ち込んだ。
それからもはやこの山には、化物は出んようになったそうな。
丹原井手の人柱
竹の内部落の東山すそを流れている水路を「丹原井手(たんばらいで)」という。
これは勝田川の水を堰(せき)止めて井出を作り、水田灌漑をやって農業を営んでいたが、大雨の降るたびに大水となり堰を流し村人を困らせていた。
こうした人と水との闘いが続いていて、堰の修理を多くの人達でやっており、誰というとなく「人柱を立てると流れんようになるそうな」と話していた。
丁度そのやさき、偶然に丹波の国から来たという親子三人の乞食が現れた。
部落の者が相談してこの乞食に人柱になってくれといった。「私は足の悪い乞食だが役に立つなら人柱にしてくれ」といって進んで人柱になった。
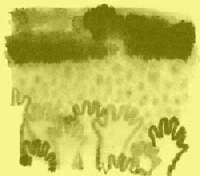 これを知った乞食の母親と子供は、泣き泣き西の山に逃げ込んだ。 これを知った乞食の母親と子供は、泣き泣き西の山に逃げ込んだ。
母親の入った谷を「親泣谷」、子供の逃げ込んだ谷を「子泣谷」と呼んでいる。
そして、父親を人柱にして作った堰は、その後どんな雨が降っても流れることがなくなり、この井出を誰が言うともなく「丹原井手」というようになった。
日照が続く時は、乞食を埋めた上の石を叩くと必ず雨が降るといわれ、又、この堰を修理するたびに雨が降る。
これは父親をしのんで母子が泣く涙雨だと、言い伝えられている。西の山へ逃げ込んだ母子は、泣きながら山を登り立子谷へ越して行った。そして谷をとおり、川を渡って平たいところにたどりついた。そこで父親の死を悲しみ、鈴を鳴らして幾日も幾日も供養をしたのだそうだ。鈴の音を聞いていた村人はこの場所を「鈴ケ平」と言うようになった。又、食べ物はなくなり、寒さはきびしくなってくるし、母子はたびたび喧嘩をしていたようだ。それでこの場所を「喧嘩ケ平」といっている。
又、将来をはかなんで二人は別れ別れに近くの谷に入り腹を切って死んだといわれ、母親のなくなった谷を「胴切り」、子供のなくなった谷を「小胴切」と呼んでいる。
釈迦平の大蛇退治
大熊部落の西山に釈迦平と言うところがあり、そこに阿弥陀堂が建っていました。
そして、その庭に七つの池があり、その池の底はつながっているといわれています。この池はどんなに日照が続いても、水は少しも減ることがありません。
 また、どんなに雨が降って、周辺の川の水がふえても、池の水かさは増えません。 また、どんなに雨が降って、周辺の川の水がふえても、池の水かさは増えません。
ところがこの池には大蛇が住んでいて、時々、人里に出かけては付近の人々を苦しめておりました。
ある年、このうわさを蟹財蔵というお奉行さんが聞き、たくさんの人夫を連れてきて、昼も、夜もかかって、この池を埋めてしまい大蛇を生け捕りにしました。
それ以後、村は大蛇に苦しめれれることはなくなりました。
平田ケ平と狐
平田ケ平部落の始まりは、いつ頃かよくわからないが、谷の西側で、小高い所の、よく日の当たるところから、日当たり平となり、のちに「平田ケ平」となったようだ。
昔この付近には夕方になると、スケタラ谷の狐が出てきて、二の瀬の橋で、荒神さん参りの人が、一杯きげんで帰ってくるのを待ち受けていた。
その日も、村の酒好きなお爺さんが、かかさんの土産に塩マスを、子供の土産にまんじゅうを買って、一杯きげんで、この橋を渡ろうとしたら、きれいな女が、姉さんかぶりに手ぬぐいをかぶり、後から追いついてきて「ええところに連れていったげるけえ、来なはれな」というので、つい、ふらり、ふらりとついて行って見ると、立派な一軒家があり、中には誰もおらず、その女が、いそいそとごちそうしてくれて、楽しい一夜を過ごした。朝になり、ふと眼をさまして見たら、これはしたり、山の中の草むらに、一人で寝ており、ごちそうは馬の糞や木の葉だけ。そして買物の塩マスも、まんじゅうも、影も形もなくなっていた。
それから村人は、「見知らぬ女に出会ったら、その足元を見よ。狐は顔は化けても、足元は化けられず小さいので、見分けがつくけなぁ」といいあったということです。
三軒木地
昔、船上山のふもとの東と西に、三軒づつ木地屋があった。東側を負子谷、西側を障子(精進)川と呼んでいた。この六軒の木地屋は原木の取り合いや、商い事などで大変仲が悪く、何かにつけて争いの絶え間がなく、とうとう木地師が信仰している、山の神さんに藁人形を打ちつけたりして呪い合ったそうな。
そこで、とうとう西の木地屋の者は、病気になったり、跡取りがなくて絶えてしまった。そして、この亡霊の恨みで、その屋敷の跡地には、アザミなどの雑草が生い茂り、狐籔とも、狐が住みつき人を化かすともいって、東村の者は寄りつかなかった。今では、アザミ谷という地名だけ残っている。昔の影はまったく見られない。
鯖をくわえた幽霊
昔、以西のある部落のはずれにケチで有名な、おじいさんと、おばあさんが住んでいた。朝は明るくなってから起き、日が暮れると床についた。あんどんの油を使わないためだ。
食事の時には梅干一つづつと、醤油が一合あれば一年はおかずはいらない。膳に向かい、まず梅干をなめる。そのすっぱさで飯を食う。時々箸の先に醤油をちょこっとつけておかずにした。
こんなふうだから、魚屋が魚を売りに行っても、いわし一匹も買ったことがない。ある日、魚屋が「なんぼケチでも、ただなら食うだらあ…」と、裏口に生きのいいサバを一匹置いて物かげから見ておった。しばらくすると「じいさん大変だ」と、おばあさんの素っとん狂な声がして、おじいさんが顔色をかえてとんできた。二人はしばらくしゃがみこんで、そのサバをじっと見つめていた。「じいさん、うまそうだなあ…」、「うーん」。だまって見ていたが、やがて立ち上がったおじいさんは「飯どろぼうめ、この飯どろぼうめが」といいながら、杖の先でこのサバをつつき、とうとう溜めつぼの中に突き落としてしまった。これを見ていた魚屋は、「こりゃひょうばん以上のケチだわい…」とびっくりしたそうな。
 それから何ヶ月かたったある日、おばあさんはやせ衰えて死んでしまったそうな。葬式も簡単に済ませて、初七日の夜、おじいさんは何時ものように、日暮れとともに床に入ったが、寝付かれないまま真夜中になった。かすかに月明かりが障子を明るくしている。その時、仏壇からヒューという音がして、白木の位牌がコトンと倒れた。おじいさんは「不思議だなあ、風もないのに」といいながら、あんどんに灯りをつけて仏壇の方を見ると白い髪を振り乱し、口にサバをくわえたおばあさんの顔が浮かんで見えた。そして一言、「おじいさんサバがうまいけ、食ってみなはれ」といい、スウーと消えた。じいさんは頭から布団をかぶり、ブルブル震えながら朝を待ったそうな。 それから何ヶ月かたったある日、おばあさんはやせ衰えて死んでしまったそうな。葬式も簡単に済ませて、初七日の夜、おじいさんは何時ものように、日暮れとともに床に入ったが、寝付かれないまま真夜中になった。かすかに月明かりが障子を明るくしている。その時、仏壇からヒューという音がして、白木の位牌がコトンと倒れた。おじいさんは「不思議だなあ、風もないのに」といいながら、あんどんに灯りをつけて仏壇の方を見ると白い髪を振り乱し、口にサバをくわえたおばあさんの顔が浮かんで見えた。そして一言、「おじいさんサバがうまいけ、食ってみなはれ」といい、スウーと消えた。じいさんは頭から布団をかぶり、ブルブル震えながら朝を待ったそうな。
それから毎晩、毎晩真夜中になると幽霊が現れ、おじいさんは悩まされ続けて間もなく死んでしまった。
空き家になったこの家には、幽霊が出るということで住む人もなく、荒れ果てていたが、ある日、村の若者が集まって「何が幽霊なんぞ出るだい、今夜はあの家でいっぱい飲まあぜ」と話がまとまり、夕方になるとそれぞれ酒や肴を持って集まった。いろりを囲んでにぎやかに酒盛りが始まり、夜も更けてくると一人つぶれ、二人つぶれ、とうとう酒に強い二人が残った。「みんなのびてしまったなあ…」と静かになって何か心細くなり、ちょろちょろ燃えるいろりの火を見つめていた時、仏壇からヒューと、音がして、白木の位牌がコトンと倒れた。変だと思いながら一人がその位牌を起こそうと仏壇に近づいた時、白い髪を振り乱し、サバをくわえた老婆の顔が現れた。「ギャー、出た!」と叫んで、その若者はその場に倒れた。その声に驚き、他の者も飛び起きた。みんなも腰を抜かし、ふるえながら、はうようにしてこの家を出た。
それからは、この家に近づく者はなかったということだ。
がんばされの滝
大熊の西の山に、滝流れがあり、その滝を「がんばされの滝」といった。
昔、西の方から、得体の知れないうなり声が、三日三晩続いた。
村の衆が不思議に思って、何かおおごとが起きているかも知れないと、村の若い衆多勢に様子を見に行かせた。すると、その滝に今まで見たこともない大きな蟹が、岩と岩の間にはさまって動くことも出来ず、大泡をふいておった。
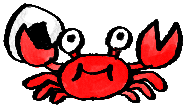 「なんと村の若衆助けてごっされ」と蟹が、たのんだ。しかし、これまで村の田畑を荒らしまわるものがおったが、その正体を見たものがなく「おのれが、これまで田畑を荒していただらあが、たすけてやるもんか」と村の衆はみんなで蟹を生け捕りにして帰った。そして村中で蟹料理をして食い、甲羅は村の庄屋さんの家の天井に、また足殻は、なんと小便受けになったそうな。 「なんと村の若衆助けてごっされ」と蟹が、たのんだ。しかし、これまで村の田畑を荒らしまわるものがおったが、その正体を見たものがなく「おのれが、これまで田畑を荒していただらあが、たすけてやるもんか」と村の衆はみんなで蟹を生け捕りにして帰った。そして村中で蟹料理をして食い、甲羅は村の庄屋さんの家の天井に、また足殻は、なんと小便受けになったそうな。
和尚と小僧
昔のことだが、和尚が小僧にかくれて、時どき夜食を食べていた。時には、鮎の寿司を買って食べたりしていた。たまたま小僧がそれを見つけて「和尚さん、今のは何だっただいな」といったら和尚さんは「今、ひげ剃らあと思って、剃刀だいとっただぁ」といってごまかしてしまった。
ある日、その和尚さんが馬に乗って大父木地へ法事に出かけた。小僧は後からついていった。そしたら、川にたくさん鮎が泳いでいて小僧は和尚さんに、皮肉っぽく「はあ、和尚さん、和尚さん、剃刀が、がいにおって遊んでいますなあ」といった。「見たのは見逃し、聞いたことは聞き逃し、しとるもんだ」と、いった。
しばらく歩いていると和尚のしゃっぽが落ち、和尚さんが「落ちるのを見たか」と聞いたところ、小僧は「見たのは見逃しとれ、といわはるだけ見逃しとりました」と答えた。
 和尚は、少し怒った調子で「馬から落ちたものは、みんな拾え」と小僧に言ったところ、たまたま馬が糞をした。小僧は、しゃっぽにそれを入れて、和尚に差し出した。 和尚は、少し怒った調子で「馬から落ちたものは、みんな拾え」と小僧に言ったところ、たまたま馬が糞をした。小僧は、しゃっぽにそれを入れて、和尚に差し出した。
和尚は、そのことをとがめたところ、小僧は、「これ、みんな馬から落ちてきましたで」といった。
和尚は何も言うことが出来ずに「つくづく小僧ちゅうもんは、みんなしょうの辛いもんだ」と思ったそうだ。
重六さんの狼取り
昔々、大父の村近くに狼が住んでいて、山羊や鶏は喰われるし、村人もたびたび襲われるので、子供は家から外に出さないようにし、畑仕事には、何人か一緒になって出かけたりして、大変恐れていたそうな。
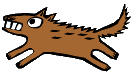 ある朝、重六さんという大変親孝行な、働き者の若者が、いつものように朝早く、鎌を持って草刈に出かけた。 ある朝、重六さんという大変親孝行な、働き者の若者が、いつものように朝早く、鎌を持って草刈に出かけた。
村はずれに差し掛かった時、まだ薄暗い道端の草むらの中から、眼をらんらんと光らせた真っ黒な狼が、重六さん目がけて飛びかかってきた。重六さんは、とっさに腰を落とし、持っていた鎌を横に払った。なにぶん研ぎたての鎌だったので、狼の腹を真一文字に切り裂いた。狼は真っ赤な血を一面にたらし、もんどりうって、その場に倒れ死んでしまった。
その後、大父の村では、狼も出なくなり、村人は安心して、家畜を飼ったり、畑や山仕事ができるようになり、子供たちは元気に外で遊べるようになって、たいそう喜び、今でも村の語り草になっている。
大熊の天皇水
後醍醐天皇が、船上山より京都にお帰りになるとき、大熊村で、にわかに喉が渇き、水を一杯求められました。ところが、この村には、天皇に差し上げる飲み水がなく、困っていました。
すると、天皇は、そこにある大岩を指差され「みなの者、心配しなくてもよい。この岩を起こせば必ず水が湧き出るであろう」とおおせになりました。
そこで、居合わせた力持ちの村人が、大力をこめて大岩を起こすと、清水がコンコンと湧き出してきたではありませんか。
天皇はたいそうお喜びになり「この村には、大変な強力者がいる」とお褒めになり「強力」の姓を与えられました。そして、この清水を「天皇水」と名づけ、その流れを神川(かんがわ)として大事に守り続けてきました。
のちに強力を「高力」と改め、今なお三十戸あまりの村のほとんどが「高力」を名乗っているのです。
|

